はじめに:「ことばの遅れ」ってどういうこと?
「うちの子、まだお話ししないけど大丈夫かな?」「同じ年の子はもっとしゃべってる…」
ことばの発達には個人差があり、比べることに不安を感じる保護者の方も多いでしょう。
「ことばの遅れ」とは、同年齢の子どもと比べて言葉の理解や発話の面で発達がゆっくりな状態を指します。ただし、すべての「ゆっくり=問題」とは限りません。周囲の環境、性格、家庭での言語経験など、さまざまな要因が影響します。
この記事では、ご家庭で今日からできる5つのステップをわかりやすくご紹介します。
「まだ様子を見ていいのかな?」と悩む方にこそ読んでいただきたい内容です。

ことばの発達の目安(月齢別チェックリスト)
ことばの発達は、理解 → 発声 → 会話へと段階的に伸びていきます。以下は、おおまかな目安です。
0〜6ヶ月頃
- 声や音に反応する
- 「あー」「うー」など喃語が出てくる
7〜12ヶ月頃
- 名前を呼ぶと振り向く
- 「まんま」「ぶーぶ」など意味のある音を言う
1歳〜1歳半
- 簡単な指示(「ちょうだい」「バイバイして」など)を理解する
- 「ワンワン」「ママ」など意味のある単語が増える
1歳半〜2歳
- 「もうすこし」が分かる
- 「パン たべる」など2語文が出始める
2歳〜3歳
- 質問に答えるようになる
- 「どこ?」「なに?」など質問が増える
月齢通りでなくても、少しずつ増えている・理解が広がっていることが大切です。
家庭でできることばの発達サポート(年齢別・簡単な声かけ例)
ことばの発達は、毎日の関わりで育っていきます。特別な教材や難しい知識がなくても大丈夫。以下のような「ことばを育てる声かけ」を意識してみましょう。
0〜1歳
- 「あっ、音がしたね」「見て見て、ワンワンだよ」など、五感とリンクさせた語りかけ
- 泣いたら「お腹すいたのかな?」「抱っこしてほしいの?」など気持ちを代弁する
1歳〜2歳
- 「ボール ころころ」「リンゴ たべる」など短い言葉で実況中継
- 「どっちにする?」「これはなに?」と選択肢や問いかけを増やす
2歳〜3歳
- 「今日、公園でなにしたっけ?」とふりかえりトーク
- 子どもの言葉を繰り返す:「わんわん きた」→「そうだね、ワンワン来たね!」
子どもが話さなくても、親が語りかけ続けることが発達の土台になります。
無理に話させようとせず、「聞いてもらえて嬉しい」と思えるやり取りを意識しましょう。
「ことばの遅れ」があっても今できること
「話さない=遅れている」と決めつける必要はありません。言語聴覚士の立場から、ご家庭で“今”できることをお伝えします。
1. 焦らず観察して記録をとる
- 単語数、ジェスチャー、声かけの反応などをメモしてみましょう。
2. 遊びを通して関わる
- ごっこ遊び、積み木、絵本など、道具より「やり取り」を重視
- 「〇〇しよう!」より「〇〇どうする?」と双方向のやりとりを増やす
3. 相談できる場所を知る
- 市町村の健診や保健センター
- 発達支援センター・子育て支援センター
- 必要に応じて言語聴覚士のいる医療機関へ
受診や支援は「困ってから」ではなく「気になる時」に相談してOKです。
早めの相談は、保護者の安心にもつながります。
よくあるQ&A:「様子見でいい?」という不安への答え
Q1:「まだ2歳だから、様子を見ていいですか?」
年齢だけで判断せず、「理解の程度」「やり取りの様子」で見ましょう。気になるなら専門機関に相談しても大丈夫です。
Q2:「スマホやテレビは影響しますか?」
長時間の一方向な視聴は、ことばのやり取りを減らす原因になります。
一緒に見て話しかけることで質を高められます。
Q3:「兄弟が話し始めたのが遅かったので、遺伝ですか?」
確かに家族の傾向はありますが、それだけが原因ではありません。
個別に見て判断する必要があります。
Q4:「今からでも間に合いますか?」
はい、大丈夫です。ことばの力は、3歳以降でも伸びていきます。
焦らず、今できることから始めましょう。
おわりに:お子さんのことばの力を信じて
ことばの遅れがあると、心配や不安が大きくなるものです。
でも、ことばは「教え込むもの」ではありません。
おうちでの関わりや、ちょっとした声かけが、子どもにとって大きな支えになります。
「ことばの遅れ」は、お子さんが「ことばの力を育てている途中」です。
今できるステップを、焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。
必要な方は、記事をブックマークしていつでも見返せるようにしておくのがおすすめです。
今後、無料教材配布を予定しておりますので面白そう!と思ったものを印刷して使ってみてくださいね♪
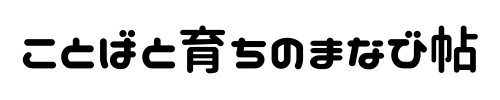
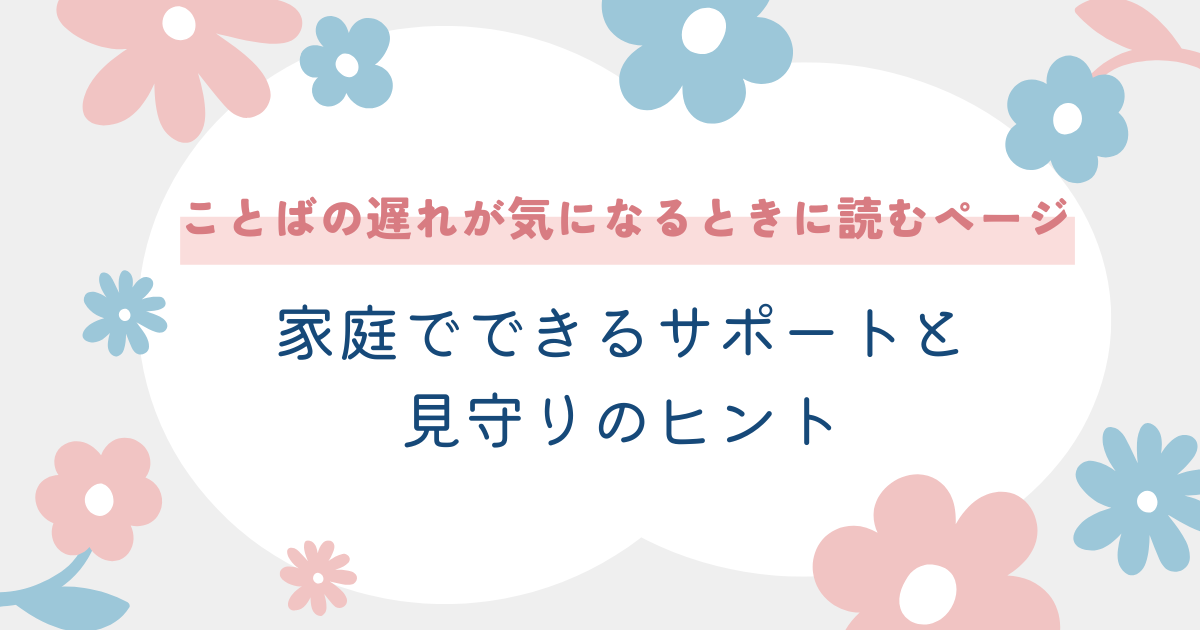

コメント