「うちの子、まだ『サ』が『タ』みたいに聞こえるけど大丈夫?」
「『ラ』の音が言えなくて心配…」
子どもの発音について、こんな不安を感じている保護者の方は多いのではないでしょうか。
実は、子どもがつまずきやすい音には 傾向 があり、発達の順序の中で「後から完成する音」があるのです。
この記事では、言語聴覚士の立場から、発音が難しい理由やつまずきやすい音の特徴をわかりやすく解説します。
発音しにくい音には傾向がある
出やすい音と出にくい音の違い
発音には、「比較的出やすい音」と「難しい音」があります。
- 出やすい音:口を閉じて「パ」「マ」「バ」など、単純な唇の動きだけで出せる音。
- 出にくい音:舌の位置や息のコントロールなど、複雑な調整が必要な音。
つまり、口の動きがシンプルな音は早く出やすく、舌や息の調整が必要な音は後から身につくのです。
年齢による差
発音の完成には個人差がありますが、一般的には以下のような順序があります。
- 2〜3歳頃:パ・マ・タなどシンプルな音が出やすい
- 4〜5歳頃:カ行やサ行など複雑な音が少しずつ整う
- 5〜6歳頃:ラ行や「ツ」「チ」などの音が完成
「まだ言えない音がある=遅れている」わけではなく、自然な発達の順序なのです。
よくつまずく音の特徴と理由
【サ行】空気のコントロールが必要
「サ」「シ」「ス」「セ」「ソ」は、舌の位置と息のコントロールがポイント。
舌のすき間から細く息を出す必要があるため、まだ口の使い方に慣れていない子には難しく感じられます。
【カ行】舌の奥を持ち上げる動きが難しい
「カ」「キ」「ク」「ケ」「コ」は、舌の奥を持ち上げて発音します。
3〜4歳ごろまでは「タ」に置き換わることもあります。
【ラ行】舌先を「はじく」動きがまだ苦手
ラ行の音は、舌の先を上あごに軽く当てて、すばやくはじくことで出す音です。
この動きは細かくて難しいため、子どもにとっては最後の方に身につく発音のひとつです。まだ舌を上手にはじけないうちは、「ら」が「だ」に聞こえることもあります。

家庭でできるサポートのポイント
子どもの発音をサポートしたいと思う親御さんも多いですが、注意してほしい点があります。
- 無理やり言い直しをさせない:「違うでしょ、もう一回言って!」と繰り返すと、子どもが話すこと自体を嫌がることがあります。
- 正しい発音をさりげなくモデルにする:「たかな」→「そうだね、さかなだね」と、自然に正しい言い方を聞かせるのが効果的です。
- 焦らず見守る:発音には発達の順序があります。今できていなくても、成長とともに身につくケースがほとんどです。
大切なのは、発音を矯正することよりも「話す意欲」を育てることです。
そして、もし発音の不安が強く、日常生活に支障を感じるようであれば、
前回の記事でお伝えした相談先(地域の言語聴覚士や発達相談窓口など)に連絡してみるのも安心につながります。

まとめ
子どもがつまずきやすい発音には理由があります。
- 単純な口の動き → 早く出やすい
- 舌や息のコントロールが必要な音 → 遅く完成する
特に「サ行」「カ行」「ラ行」は多くの子がつまずきやすく、成長とともに改善していきます。
「今はまだ言えない音がある」というのは、発達の自然な過程なのです。
👉 次回は「発音」と「音韻意識(ことばを音として意識する力)」の関係について紹介します。

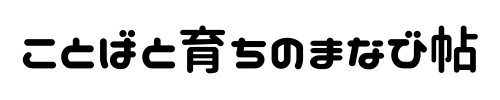



コメント